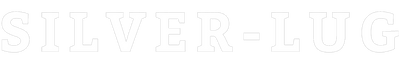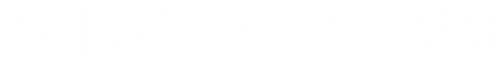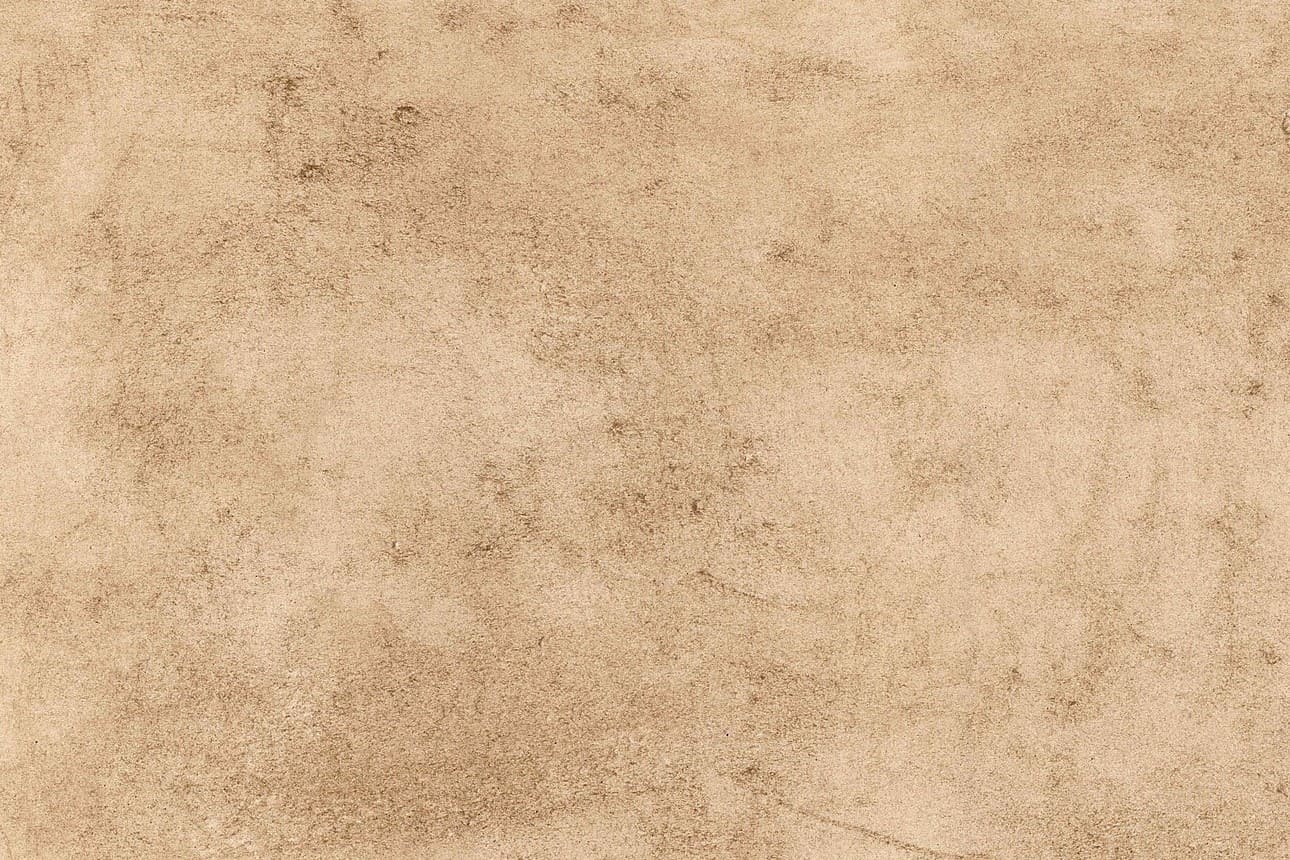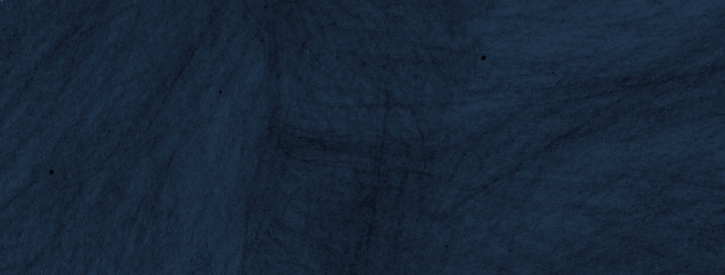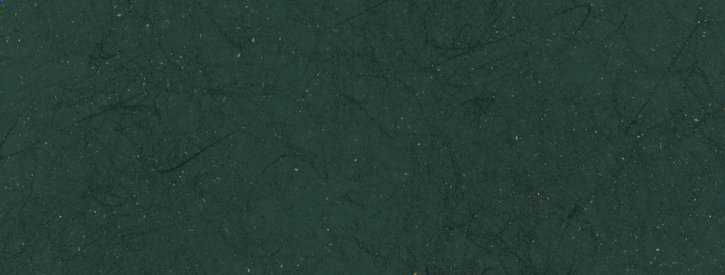日本でスターリングシルバーを”純銀”と表記する理由
投稿日: 投稿者:WATANABETAIGA

西洋アンティークの銀製品を扱う中で、お客様から時折いただく質問があります。
「商品説明に『純銀』とありますが、刻印を見るとスターリングシルバーですよね? なぜ純銀と表記するのですか?」
銀の純度について少しでも知識のある方であれば当然の疑問です。
化学的に言えば、純銀は99.9%以上の純度を持つ銀(SV999)を指し、スターリングシルバーは銀の含有率が92.5%の合金(SV925)です。
しかし、日本のアンティーク業界でスターリングシルバーを「純銀」と表現するのは、単なる言葉の間違いではなく、数百年にわたる西洋の歴史とそれを日本で受け入れてきた文化的な背景に基づいた、深い理由が存在します。
この記事では、なぜ私たちがスターリングシルバーを「純銀」と呼ぶことがあるのか、その背景を言葉の意味や歴史を紐解きながら解説いたします。
1.英語におけるそれぞれの単語の意味と「スターリング」の語源
まず、混乱を避けるために、基本となる言葉の定義から整理していきます。
銀製品について語る際、英語圏では主に以下の言葉が使われます。それぞれの意味合いは微妙に異なります。
Fine Silver / Pure Silver(ファインシルバー / ピュアシルバー)
化学的な意味での「純銀」です。銀の含有率が99.9%以上(999/1000)のものを指します。
その輝きは白く美しいものですが、非常に柔らかく少しの力で曲がったり傷ついたりしてしまいます。
そのため、食器などの日常的に使う製品の素材としては、ほとんど用いられることはなく、主に地金や記念コインなどに使用されます。
Sterling Silver(スターリングシルバー)
銀の含有率を92.5%(925/1000)とし、残りの7.5%に銅などの金属(割り金)を加えた合金です。
割り金を加えることで、純銀の美しい輝きを損なうことなく、実用的な強度と耐久性を高めることができます。
この絶妙な配合比率が、西洋(特に英国)の銀製品における世界的な標準規格となりました。
Solid Silver(ソリッドシルバー)
「銀無垢(ぎんむく)」と訳される言葉で、「中まで全てが銀の合金でできている」という意味です。
表面だけに銀を施した「銀メッキ」と区別するための表現であり、特定の純度を指す言葉ではありません。
したがって、スターリングシルバー(92.5%)も、ヨーロッパ大陸で使われた80.0%の銀も、すべて「ソリッドシルバー」に含まれます。
Silver Plate(シルバープレート)
「銀メッキ」製品のことです。銅やニッケルなどの土台の表面に、ごく薄い銀の膜をコーティングしたものです。
安価に銀の輝きを楽しめますが、長年の使用でメッキが剥がれ地金が見えてしまうことがあります。
EPNS(Electro Plated Nickel Silver)などの刻印で区別されます。
シルバーの種類や純度に関してはこちらのブログ記事もご参照ください
「スターリングシルバー」の語源
最も有力なのは、11世紀頃のノルマン朝イングランドで造られた「ノルマン・ペニー」という銀貨に由来するという説です。
この硬貨には、品質の証として小さな星(古英語で steorling)が刻まれていました。
この「星付きの硬貨」が「スターリング」と呼ばれ、やがてその硬貨が持つ「銀92.5%」という品位そのものを指す言葉になった、とされています。
もう一つの説は、中世にバルト海沿岸で活動していた「イースターリング(Easterling)」と呼ばれる北ドイツの商人たちがイギリスに持ち込んだ銀貨です。
この銀貨は品質が非常に高く信頼されていたことから、「イースターリング・シルバー」と呼び、それが短縮されて「スターリング」になった、というものです。
どちらの説が正しいかは定かではありませんが、共通して言えるのは、「スターリング」という言葉が、「信頼できる、品質の保証された銀」という意味合いを強く持っていたということです。
この言葉は単なる合金の名称ではなく価値の象徴でした。
そしてこの意味合いは、後にホールマークによる国家による厳格な品質保証制度によって、絶対的なものになっていきます。
2.日本におけるシルバーの純度
欧米で「スターリング」という基準が確立されていった頃、日本では銀の純度をどのように扱っていたのでしょうか?
結論から言うと、中世から近世にかけての日本には、国が定めた統一的な純度基準というものは、西洋のそれとは異なる形で存在しました。
鎌倉時代から戦国時代にかけて、銀は主に重さで取引される地金(じがね)として流通していました。
石見銀山などで産出された銀は、「灰吹法(はいふきほう)」という精錬技術によって純度を高められ「灰吹銀」として市場に出回りました。
しかし、その品位は一定ではなく取引のたびに見た目や試金石などで質を確かめ、当事者間の合意で価値が決められていました。
そこには、国家による客観的な保証は存在しなかったのです。
この状況が大きく変わるのが江戸時代です。
徳川幕府は貨幣制度を統一するため、銀貨の鋳造と品位の管理を専門に行う「銀座(ぎんざ)」を設立しました。
ここで造られたのが、「丁銀(ちょうぎん)」や「豆板銀(まめいたぎん)」といった、重さを測って使用する「秤量貨幣(ひょうりょうかへい)」です。
銀座は、鋳造した丁銀の表面に「極印(ごくいん)」と呼ばれる刻印を打ちました。
代表的なものに、大黒様の図案や「寳」の文字があります。この極印こそが、その銀貨が幕府の定めた品位であることを証明する、日本独自の品質保証でした。
これは、西洋のホールマーク制度と同じ役割を担うものと言えます。

しかし、西洋のスターリングシルバーと決定的に違う点がありました。
それは、品位が一定ではなかったことです。
例えば、江戸時代初期の慶長丁銀の銀品位は約80%と定められていました。
しかし、幕府は財政が厳しくなると利益を得るために銀の含有量を減らした新しい銀貨を造り直す「貨幣改鋳」を度々行いました。
元禄時代には約64%、その後には50%を切るものまで登場します。
つまり、日本の銀制度は常に変動する可能性があるものでした。
絶対的な基準として長期間固定されたスターリングシルバーとは、その根本的な思想が異なっていたのです。
3.日本でスターリングシルバーを「純銀」と表記する理由
さて、ここまでの背景を踏まえて、いよいよ本題です。
なぜ、日本では純度92.5%のスターリングシルバーを「純銀」と表記する慣習が生まれたのでしょうか。
それは「化学的な純度」よりも「歴史的に保証された価値」を重んじた結果であり、明治時代に西洋文化を受け入れた際の日本人の解釈の仕方に起因します。
話は14世紀のイギリスに遡ります。
1300年イギリス国王エドワード1世は、銀製品の品位がスターリング(92.5%)の基準に満たない限り、販売を許可しないという法律を制定しました。
そして、専門の機関(アセイ・オフィス)が品位を検査し、合格した製品にだけ刻印(ホールマーク)を打つ制度を確立します。
このライオンパサント(横歩きする獅子)の刻印は、その銀製品が「スターリングシルバーであること」を国家が証明する、世界で最も信頼される品質保証の証となりました。
英国のホールマークについてはこちらのブログ記事もご参照ください
この制度の下では、実用的な銀製品においてスターリングシルバーこそが「法的に認められた最高品質の銀」でした。
柔らかすぎる化学的な純銀(Fine Silver)は市場にはほとんど存在せず、人々にとって「本物の、価値ある銀」とは、まぎれもなくスターリングシルバーのことだったのです。
それは単なる合金ではなく、国家の権威によってその価値が保証された特別な存在でした。
時代は下り、明治時代の日本。西洋の文化や製品が堰を切ったように流入してきました。
そこには、何百年もの間、品位を変えることなく国家が品質を保証し続けてきた、絶対的な信頼性の証であるホールマークが輝いていました。
時代によって品位が変動した日本の銀貨とは対照的に、その価値は不変でした。
この「Sterling Silver」という概念を日本語に翻訳する必要に迫られたとき、当時の人々は、その価値を最も的確に表現する言葉を探したはずです。
単に「銀92.5%の合金」と訳すだけでは、その背景にある権威や信頼性、そして「実用銀における最高品質」という意味合いが抜け落ちてしまいます。
そこで選ばれた言葉が「純銀」だったと考えられます。
当時の日本において、一般の人々が日常で触れる銀製品はまだ少なく、「純」という言葉は「まじりけのない」「本物の」といった、価値の高さを直感的に伝える響きを持っていました。
化学的な正しさよりも「これこそが西洋における本物の、価値の保証された銀なのだ」というニュアンスを伝えるために、「純銀」という言葉が最もふさわしいと判断されたのだと推測されます。
この解釈は、その後日本のアンティーク業界や宝飾品業界に一つの慣習として深く根付きました。
ディーラーや蒐集家たちは、ホールマークが刻まれたスターリングシルバーを「純銀」と呼ぶことで、その製品がメッキなどではない「本歌(ほんか)」であり、歴史と信頼に裏付けられた本物の価値を持つ品であることを示してきたのです。
まとめ
私たちがアンティークのスターリングシルバー製品を「純銀」と表記することがあるのは、決して化学的な定義を無視しているわけではありません。
それは、この言葉が持つ歴史的な重みと、業界に受け継がれてきた文化的な慣習を尊重しているためです。
この「純銀」という表記には、
・欧米でスターリングシルバーが「実用的な銀製品の最高品位」として国家に保証されてきた歴史
・明治の日本人が、その絶対的な価値を理解し「本物の銀」として受け入れた際の解釈
・アンティーク業界が、その歴史的価値への敬意を込めて使い続けてきた、文化的な言葉
といった、幾層にも重なった意味が込められています。
当店では、スターリングシルバー製の商品のタイトルには「純銀」と表記しておりますが、お客様に誤解を与えないよう、商品説明の「詳細」部分には「材質 スターリングシルバー(925/1000)」といった形式で記載しています。
アンティークの銀製品に刻まれたホールマークは、単なる純度の表示ではありません。
それは、何百年もの時の流れにも揺るがなかった「信頼の証」です。
その証を持つスターリングシルバーを先人たちが敬意を込めて「純銀」と呼んだ、背景にある物語を感じながら目の前にある一品を眺めていただけると、アンティークシルバーの持つ魅力が、また一つ深まるのではないかと思います。